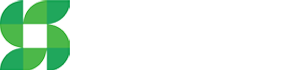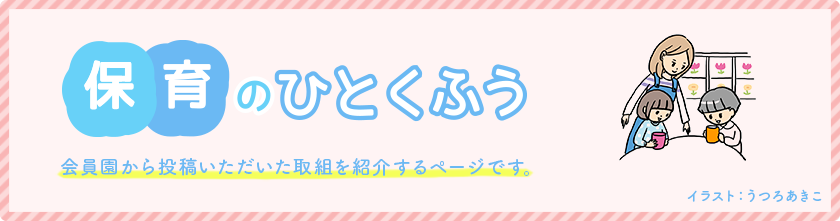保育園における緑化は、「清涼感が高まる」「温暖化をやわらげる」「疲労感をやわらげる」などすべての効果について期待度が高く、目に入る緑が多いというだけで、真夏日の不快感をやわらげるのに役立てると考えています。
保育園における緑化は、「清涼感が高まる」「温暖化をやわらげる」「疲労感をやわらげる」などすべての効果について期待度が高く、目に入る緑が多いというだけで、真夏日の不快感をやわらげるのに役立てると考えています。
 また、「季節の花や緑を観賞する場所」「ガーデニングを楽しむ場所」など花や緑に関わることで、子どもたちが自然を学び想像力を高めるとともに、コミュニティの交流の場としての活用も可能と考えられます。そんな日々の生活において保育室の中では目に触れることの多い観葉植物は大切な存在です。
また、「季節の花や緑を観賞する場所」「ガーデニングを楽しむ場所」など花や緑に関わることで、子どもたちが自然を学び想像力を高めるとともに、コミュニティの交流の場としての活用も可能と考えられます。そんな日々の生活において保育室の中では目に触れることの多い観葉植物は大切な存在です。
 観葉植物の葉は、光合成をすることが大きな目的ですが、その葉の形に目を向けてみると様々な形があり、とてもユニークな形のものも存在します。
観葉植物の葉は、光合成をすることが大きな目的ですが、その葉の形に目を向けてみると様々な形があり、とてもユニークな形のものも存在します。
ユニークで不思議な形の葉は、インテリアデザインの一部としてだけでなく子どもたちの好奇心を抱く環境の一部としても当園では、いつも触れることが出来るようにしています。