- 開催日程
- 令和3年7月7日~9日
- 開催場所
- CiscoWebexによるオンライン開催
1日目は、玉川大学教育学部教授の大豆生田啓友氏による講義・ワーク「多様な視点を得るために保育をひらく」、2日目は、オンラインでの公開保育・事例報告(幼保連携型認定こども園寺子屋大の木)、こども教育宝仙学大学こども教育学部准教授の富山大士氏よる講義・ワーク「一人一人が輝く園風土を築くために現在(いま)の保育をひらく」、3日目は、桜花学園大学保育学部保育学科教授の上村晶氏による講義・ワーク「繋がりを大切にする組織をつくるために保育をひらく」を行っていただきました。
参加された皆様が、3日間を通しオンライン上で繋がり互いに学びを深め合ったことで、「保育をひらく」ということについて新たなイメージを共有できたのではないかと思います。ご参加いただきました皆様、お疲れ様でした。
※詳細につきましては「保育通信」10月号に報告を掲載しますので、ご覧ください。
(佐藤祐美/全私保連研修部)
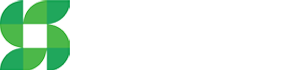


 1日目は塚本秀一全私保連常務理事より情勢報告、次に誠美保育園園長の折井誠司氏と塚本秀一常務理事から「保育の質を高めるための働きやすい職場づくりについて考える」をテーマに実践報告がありました。
1日目は塚本秀一全私保連常務理事より情勢報告、次に誠美保育園園長の折井誠司氏と塚本秀一常務理事から「保育の質を高めるための働きやすい職場づくりについて考える」をテーマに実践報告がありました。 2日目は「保育の質向上のために必要な協働的風土」をテーマに、東京立正短期大学の鈴木健史氏に講演とワークを進めていただきました。午前はまず千葉県富津市の和光保育園副園長の鈴木秀弘氏の実践発表でした。午後からは東京都葛飾区のたつみ保育園園長の塚田剛士氏より実践発表をいただきました。
2日目は「保育の質向上のために必要な協働的風土」をテーマに、東京立正短期大学の鈴木健史氏に講演とワークを進めていただきました。午前はまず千葉県富津市の和光保育園副園長の鈴木秀弘氏の実践発表でした。午後からは東京都葛飾区のたつみ保育園園長の塚田剛士氏より実践発表をいただきました。 1日目は東京立正短期大学の鈴木健史氏による「指針・要領を深く読み解く①主体的・協働的なグループワークを通じて」と題した講義・演習でした。新指針では、「保育の質及び職員の専門性の向上」のために「組織的に対応」することが求められていることを踏まえ、「関係性」や「協同性」・「同僚性」をキーワードにグループワークを通して、参加者が主体的に学び、互いに学びを共有する機会となりました。
1日目は東京立正短期大学の鈴木健史氏による「指針・要領を深く読み解く①主体的・協働的なグループワークを通じて」と題した講義・演習でした。新指針では、「保育の質及び職員の専門性の向上」のために「組織的に対応」することが求められていることを踏まえ、「関係性」や「協同性」・「同僚性」をキーワードにグループワークを通して、参加者が主体的に学び、互いに学びを共有する機会となりました。
 今年は、長野県・エクシブ軽井沢にて、全国各地より約50名の参加者が集い、園長セミナーが開催されました。「保育をみんなで磨き高め合うために」~多面的な視点から園長のあり方を考える~をテーマに、グループワークや学びの振り返りを取り入れながら、参加者自らが「主体的・対話的で深い学び」を体験し、充実した3日間となりました。
今年は、長野県・エクシブ軽井沢にて、全国各地より約50名の参加者が集い、園長セミナーが開催されました。「保育をみんなで磨き高め合うために」~多面的な視点から園長のあり方を考える~をテーマに、グループワークや学びの振り返りを取り入れながら、参加者自らが「主体的・対話的で深い学び」を体験し、充実した3日間となりました。
 平成30年2月5日~9日までの5日間で、和歌山県白浜町のエクシブ白浜にて保育カウンセラー養成講座第67回ステップⅠが開催されました。北は北海道、南は鹿児島県まで全国から総勢56名の方々にご参加いただきました。
平成30年2月5日~9日までの5日間で、和歌山県白浜町のエクシブ白浜にて保育カウンセラー養成講座第67回ステップⅠが開催されました。北は北海道、南は鹿児島県まで全国から総勢56名の方々にご参加いただきました。 ステップⅠは「人とのつながりを育てるための理論と方法を学ぶ・子どもや保護者の気持ちを受け止め、寄り添うための力を身に付ける」がテーマの講座です。
ステップⅠは「人とのつながりを育てるための理論と方法を学ぶ・子どもや保護者の気持ちを受け止め、寄り添うための力を身に付ける」がテーマの講座です。 最終日のお別れパーティでは、この講座で学んだ様々なワークを、言葉を使わないノンバーバルゲームで振り返ることで大いに盛り上がり、充実した5日間となりました。
最終日のお別れパーティでは、この講座で学んだ様々なワークを、言葉を使わないノンバーバルゲームで振り返ることで大いに盛り上がり、充実した5日間となりました。 平成29年12月14日~15日の2日間で保育カウンセラー養成講座第24回ステップアップが兵庫県神戸市のラッセホールにて開催されました。「保育者のための家族カウンセリングの実際」と題して、NPO法人日本家族カウンセリング協会副理事長の長谷川啓三氏をお迎えしました。
平成29年12月14日~15日の2日間で保育カウンセラー養成講座第24回ステップアップが兵庫県神戸市のラッセホールにて開催されました。「保育者のための家族カウンセリングの実際」と題して、NPO法人日本家族カウンセリング協会副理事長の長谷川啓三氏をお迎えしました。
 家族カウンセリングの理論を講義形式で学ぶのではなく、6人グループで家族カウンセリングを実践するというワーク主体の講座で、これまでの養成講座で学んできた内容とはまた違った理論と技法のため、受講者も最初は戸惑いを感じる様子でしたが、長谷川氏のユーモアたっぷりのお話しがとてもわかりやすく、すんなりと心に響いたのではないかと思います。
家族カウンセリングの理論を講義形式で学ぶのではなく、6人グループで家族カウンセリングを実践するというワーク主体の講座で、これまでの養成講座で学んできた内容とはまた違った理論と技法のため、受講者も最初は戸惑いを感じる様子でしたが、長谷川氏のユーモアたっぷりのお話しがとてもわかりやすく、すんなりと心に響いたのではないかと思います。 平成29年12月5日~12月6日の2日間で、東京都台東区の全国保育会館にて「第11回管理者のための公開講座」が開催されました。
平成29年12月5日~12月6日の2日間で、東京都台東区の全国保育会館にて「第11回管理者のための公開講座」が開催されました。 2日目には、臨床心理士の大竹直子氏より、管理者として保育に活かせるカウンセリングを学び、職員を理解するための発達心理学や職員の定着化など、興味深いテーマを交えての講義でした。
2日目には、臨床心理士の大竹直子氏より、管理者として保育に活かせるカウンセリングを学び、職員を理解するための発達心理学や職員の定着化など、興味深いテーマを交えての講義でした。 平成29年11月8日〜10日の3日間、ANAクラウンプラザホテル熊本において『新指針・要領を保育実践に活かすには〜保育の中の「幼児教育」と日々の保育を照らし合わせて』をテーマに行いました。
平成29年11月8日〜10日の3日間、ANAクラウンプラザホテル熊本において『新指針・要領を保育実践に活かすには〜保育の中の「幼児教育」と日々の保育を照らし合わせて』をテーマに行いました。 2日目は東京家政大学教授の那須信樹氏と阿久根めぐみこども園園長の輿水基氏より、主に幼児教育に焦点を絞り進めました。講義では「専門職とは自律性を持つものであり、自分に対する問いかけを忘れてはいけない」という言葉が印象的でした。午後は映像を見ながら「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」に関連付けて保育を考える実践的なワーク等を行いました。
2日目は東京家政大学教授の那須信樹氏と阿久根めぐみこども園園長の輿水基氏より、主に幼児教育に焦点を絞り進めました。講義では「専門職とは自律性を持つものであり、自分に対する問いかけを忘れてはいけない」という言葉が印象的でした。午後は映像を見ながら「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」に関連付けて保育を考える実践的なワーク等を行いました。 3日目は全私保連研修部の進行により、研修の学びを自園に持ち帰って説明できるよう、「学びのドキュメント」作りを行いました。
3日目は全私保連研修部の進行により、研修の学びを自園に持ち帰って説明できるよう、「学びのドキュメント」作りを行いました。 017年11月13日~17日の5日間で、保育カウンセラー養成講座第66回ステップⅠが長野県軽井沢町のエクシブ軽井沢にて開催されました。受講者は総勢77名で、北は北海道から南は沖縄県まで、全国から幅広い年代の方々にご参加いただきました。
017年11月13日~17日の5日間で、保育カウンセラー養成講座第66回ステップⅠが長野県軽井沢町のエクシブ軽井沢にて開催されました。受講者は総勢77名で、北は北海道から南は沖縄県まで、全国から幅広い年代の方々にご参加いただきました。 また、今回は保育士だけではなく、栄養士・学童支援員・母子生活指導員・施設長といったさまざまな役職の方々が参加され、普段、深く関わる機会が少ない立場の方との交流は貴重な時間となった様子でした。
また、今回は保育士だけではなく、栄養士・学童支援員・母子生活指導員・施設長といったさまざまな役職の方々が参加され、普段、深く関わる機会が少ない立場の方との交流は貴重な時間となった様子でした。 4泊5日の研修が終わる際には、さまざまな考えや価値観を持った人が集まった環境の中で、一緒に学んだ時間が短く感じられたというご感想や、5日間での講義や体験学習を通して得た気づきを職場でも活かしていきたいというご意見をいただきました。
4泊5日の研修が終わる際には、さまざまな考えや価値観を持った人が集まった環境の中で、一緒に学んだ時間が短く感じられたというご感想や、5日間での講義や体験学習を通して得た気づきを職場でも活かしていきたいというご意見をいただきました。