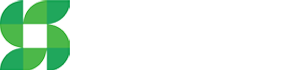自己主張は大事ですが…
鯨岡 峻(京都大学名誉教授)
大事な自己主張
7、8か月の離乳食期の赤ちゃんが、首を振って「いや、もういらない」という気持ちを伝えてくるのは、自己主張の萌芽といってもよいものです。その首を振るという行動には、たくさん食べてほしいお母さんの思いとは異なる、その子自身の思いが滲みでています。それを発端に、2歳前後になると、もうできることでも「お母さんがして」と甘えてみたり、寒いからこれを着てとお母さんがいっても「いや」と拒んだり、しだいにお母さんの思いとは異なるその子の思いが表明されてきて、これが2歳以降の強い自己主張につながってきます。
こうした子どもらしい自己主張やその萌芽は、これからその子が一個の主体として世界に進みでて、自分らしく生きていくための欠かせない大事な姿、つまり、成長してきたからこそ現れてきた大事な姿だといえます。逆に、もしもこうした自己主張が乏しく、これをしたい、これがほしい、これはしたくない、と自分の思いをお母さんに素直に伝えられないとすれば、それは一人の子どもの育つ姿としては大いに気になるといわなければなりません。特に大人の顔色を窺って聞き分けよく振る舞い、必要な自己主張をしない子どもの場合には、お母さんに聞き分けのよい「よい子」に見える分、お母さんはその子の育ちが抱える問題点に気づきにくく、今の子育てでよいのだと思い違いをしてしまいかねません。
しかし、お母さんから見れば、年齢とともに、「こうしてね」というと「いや」といい、「これは駄目よ」といっても聞き入れてくれないなど、お母さんの思いや願いと衝突することがどんどん増えてきます。そうなると、こうした子どもの自己主張は、成長したことを示す望ましい姿だと見えるよりも、聞き分けのよくない、分別のない未熟な姿だと誤解されやすくなります。
確かに、幼い子どもの自己主張は、そのすべてが大人に受け入れられるものではなく、そのために子どもとのあいだで押し問答が繰り広げられる厄介な面があることはその通りです。そこに子育ての難しい一面があることは間違いありません。それにもかかわらず、そうしたお母さんを困らせる面のある子どもの自己主張が、これからの子どもの育ちにとって欠かせない大事な意味をもっているのです。