- 開催日程
- 平成30年9月3日~7日
- 開催場所
- 静岡県・浜松市
 平成30年9月3日から9月7日の5日間にわたり、静岡県浜松市のエクシブ浜名湖において、第25回保育カウンセラー養成講座ステップⅢが開催されました。
平成30年9月3日から9月7日の5日間にわたり、静岡県浜松市のエクシブ浜名湖において、第25回保育カウンセラー養成講座ステップⅢが開催されました。2日目には、西日本に今年最大級の台風が上陸し、3日目には北海道で震度7の地震が起こり、地元に様々な思いを抱きながら受講していた人が沢山いるように見受けられました。しかし、受講生同士寄り添い、温かい連帯感が生まれていました。
2日目の「保育ソーシャルワーク」で、長谷川俊雄先生(白梅学園大学教授)の講義を受けた受講生からの感想を紹介します。
・ソーシャルワークを学ぶ、知識として持っていることの大切さを感じました。実践の中で取り入れていくこと、命を守っていることの自覚の大切さを改めて感じました。
・カウンセリングやソーシャルワークの違いを理解することができた。
 4日目の「保育カウンセリング理論と技法Ⅵ 自己生成指向カウンセリング」で、清水幹夫先生(多摩心理臨床研究所所長)の講義を受けた受講生からは、
4日目の「保育カウンセリング理論と技法Ⅵ 自己生成指向カウンセリング」で、清水幹夫先生(多摩心理臨床研究所所長)の講義を受けた受講生からは、・ロジャーズの話は難しかったが、必要なことなのだと感じました。
・グループカウンセリングを行うことで、問題がより明確になり、どの様に取り組めばいいのか理解することができた。また、ファシリテーターの役割はとても大事であり、この様な経験を沢山していきたいと思う。
等の感想がありました。
最終日には、本講座のふりかえりを行い、各々が有意義な学びを得て無事に終了することができました。今回の受講を終え、この先一人でも多くの方々が「保育カウンセラー」の道を歩まれることを願っています。
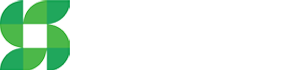







 4日目の明治大学教授の諸富祥彦氏の講義では、リレーション(人と人とのつながり)、アサーション(自分も相手も大切にした自己表現)を、グループワークを繰り返しながら学びました。
4日目の明治大学教授の諸富祥彦氏の講義では、リレーション(人と人とのつながり)、アサーション(自分も相手も大切にした自己表現)を、グループワークを繰り返しながら学びました。
 同協会の理事長である杉渓一言氏は、保育カウンセラー養成講座の立ち上げ時期から長くお力添えをいただいている関係であり、副理事長の長谷川氏から「家族カウンセリング」についての講義を実際に受けられるということは、2日間と短い期間でしたが非常に貴重な体験となりました。
同協会の理事長である杉渓一言氏は、保育カウンセラー養成講座の立ち上げ時期から長くお力添えをいただいている関係であり、副理事長の長谷川氏から「家族カウンセリング」についての講義を実際に受けられるということは、2日間と短い期間でしたが非常に貴重な体験となりました。 長谷川氏よりブリーフセラピー(問題の原因を個人に求めるのではなく、コミュニケーションの変化を促して問題を解決・解消していこうとする心理療法)のワークを通して理論を学び、個人の問題は多かれ少なかれ家族の影響を受けているものであり、家族を1つのシステムとして見ることによって、システムの歪みを発見し、そのバランスを回復するためにどのように働きかけるのか、原因探しではなく今ここで起きている事柄に対してのアプローチを学びました。
長谷川氏よりブリーフセラピー(問題の原因を個人に求めるのではなく、コミュニケーションの変化を促して問題を解決・解消していこうとする心理療法)のワークを通して理論を学び、個人の問題は多かれ少なかれ家族の影響を受けているものであり、家族を1つのシステムとして見ることによって、システムの歪みを発見し、そのバランスを回復するためにどのように働きかけるのか、原因探しではなく今ここで起きている事柄に対してのアプローチを学びました。
 淑徳大学准教授の齊藤崇氏による「保育カウンセリングトレーニング」では、ステップⅠで学んだことを丁寧に振り返りながら、保育者に何故カウンセリングが必要なのか、職場でストレスを抱えないためには何が大切かを学びました。講義の中で、「管理者がこの講座を学ぶと園の経営に役に立つと思う」というお話しがとても印象的でした。
淑徳大学准教授の齊藤崇氏による「保育カウンセリングトレーニング」では、ステップⅠで学んだことを丁寧に振り返りながら、保育者に何故カウンセリングが必要なのか、職場でストレスを抱えないためには何が大切かを学びました。講義の中で、「管理者がこの講座を学ぶと園の経営に役に立つと思う」というお話しがとても印象的でした。 多摩心理学研究所所長の清水幹夫氏による「成長指向の保育カウンセリング」では、保育現場での様々な出来事や問題を成長に繋げる考え方や方法を学び、後半は「自己生成プロセスワーク」というグループワークを行いました。自己生成とは、たくましく生きる力を育成することであり、私たちが保育を通して自己生成することの大切さを考えるきっかけとなりました。
多摩心理学研究所所長の清水幹夫氏による「成長指向の保育カウンセリング」では、保育現場での様々な出来事や問題を成長に繋げる考え方や方法を学び、後半は「自己生成プロセスワーク」というグループワークを行いました。自己生成とは、たくましく生きる力を育成することであり、私たちが保育を通して自己生成することの大切さを考えるきっかけとなりました。


 46名の受講生は、交流分析やロジャーズの理論に触れ、そして多くの演習を通して「自他を理解する・自他を受容する」という学びの一歩を踏み出しました。
46名の受講生は、交流分析やロジャーズの理論に触れ、そして多くの演習を通して「自他を理解する・自他を受容する」という学びの一歩を踏み出しました。





