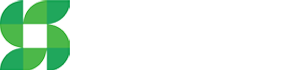…福島県伊達市・霊山三育保育園
【保育通信No.684/2012年4月号】
■じつは「ホットスポット」が点在
昨年12月15日は南相馬市にある原町聖愛保育園と北町保育所を訪問させていただきました。放射能汚染により緊急時避難準備区域に指定されてしまったことから、現場のさまざまな苦悶や苦闘、行政や東京電力に対する強い憤りを持ち、混乱と将来への展望が持てない中でも必死に保育を行い、前に進んで行こうとする姿を4月号、5月号でお伝えしました。
今号では、その翌日の16日に訪問させていただいた伊達市にある霊山三育(りょうぜんさんいく)保育園の状況をお伝えします。
伊達市は福島県の北部に位置し、福島第一原子力発電所から北西に約60㎞の場所にあります。福島原発から30㎞圏外のため、伊達市全体は政府より避難等の指示はない地域ですが、昨年3月12日に水素爆発を起こした当時の気象状況から放射性物質が多く飛散した地域であり、いわゆる「ホットスポット」がたくさん点在する場所といわれています。それを示すかのように、福島市から伊達市に移動する車中での放射線量は、南相馬市内よりも線量が高く計測される場所が多くあり、その値は0・5~0・6μsv。単純に原発からの距離で避難等の段階を区切った政府のやり方がいかに安易だったかがわかりました。
訪問当日、齋藤厚子園長先生は東京への所用でご不在であったため、代理として主任保育士の樋口先生(以下、敬称略)に対応していただきました。
■12日以降も保育を継続
樋口/当日は在籍児105名の内77名が登園していました。地震が起こった時間は、年長児たちは就学準備のため室内で保育活動を行っていて、他の子どもたちは午睡中でした。地震発生後すぐに子どもたちを起こして各保育室の中央に集め、地震がおさまるのを待っていました。しかし揺れがなかなかおさまらなかったため、齋藤園長が各保育室の様子を見たうえで園庭に避難するように指示しました。その日はとても寒かったので、ブールシートを敷いて園内から布団や毛布を持ち出し、寒さを凌ぎました。
度重なる余震の最中にも保護者のお迎えが徐々に増えて来る中、雪が降り出してきたことや、余震の回数も減ってきたこともあり、園内に戻って最後のお迎えまで待ちました。お迎えの時、泣きながら来たお母さんもいました。最後のお迎えは18時20分くらいです。そして翌12日から休園しました。
これは、原発事故の影響というよりもライフラインである電気と水道が止まったからです。もちろん、市当局と連絡を取って決めました。しかしその間も1~2名の保護者はどうしても保育をお願いしたいとの申し出があったので、このような状況でも保育は行っていました。結局、電気は13日、水道は21日に復旧したので、22日より正式に保育を再開しています。
樋口/基本的には出勤していました。ただ、小さい子どもがいる職員などは自宅待機としていました。
樋口/地震の揺れが半端ではなく、下に隠れていた机が左右に振れていたので、それに驚いて泣き出す子もいました。ただ、小さい子はよく状況がわからなかったのか、あまりの状況に呆気にとられていたのか、泣く子はそんなにはいませんでした。
樋口/とにかく揺れが大きかったので机上の物は「飛び散った」ようになり、棚などは倒れて書類は散乱し、まさに足の踏み場もないような感じでした。建物は若干傾いたようで、床にボールを置くと転がっていきます。あとは壁に少しひびが入ったり、支柱と天井との間に隙間ができたり、一番ひどかったのは駐車場にあった浄化槽が地中に陥没してしまったことです。
樋口/当園のある伊達市霊山町掛田地区はとくに何の指示も出ませんでしたが、この近辺だと霊山町小国地区などは避難指示が出たようです。その地域が一体どの程度の線量があったのかはわかりません。
現在も毎日モニタリングを行っています。室内でだいたい0・3μsv、屋外(園庭)で0・5~0・6μsvです。この値はもちろん除染後のもので、除染活動は保育園再開後に父母の手を借りて行いました。
除染の一つとして表土の入れ替えを行っていますが、表土を入れ替える前の線量は2・5μsvありました。ただ、その入れ替えで出た汚染土を保管する場所がないので、今は園庭の隅に集め、シートで覆って保管してあります(インタビュー後にこの場所を見学しましたが、保管してある土の高さと量に驚きました。盛られた土の高さは我々の背丈とほぼ同じくらいで、この付近の線量はシートで覆われていたためか約0・4μsvでした)。
樋口/除染に必要だった高圧洗浄機、デッキブラシ、窓拭き用具は現物支給されました。表土入れ替え費用は支給してくれました。
樋口/除染活動が終了した時、子どもたちのために数分でもいいから外遊びを再開したいと考え、その旨のお知らせを保護者にしたのが11月です。時間は15分間で、固定遊具は使わずに鬼ごっこや散歩を条件に保護者から同意書を得て始めました。
しかし、初めの頃は同意しない保護者も多くいて、同意した保護者の子どもが外遊びをしているのを見た子どもたちは家で「外で遊びたい」と泣いて訴えたようで、その姿を見て同意した保護者もいました。結局、同意しなかった保護者は5~6名です。
Q/11月までは外遊びをしていなかったようですが、それによる子どもたちの変化はありましたか?
樋口/そうですね、やはりテレビなどで盛んに放射能のことが報道されていて、それを常時目にし耳にしているためなのか、窓を開けると「放射能が入ってくるから開けちゃだめだよ」といったり、外に出てはいけないという認識を持っていました。また、ずっと室内での活動でしたが、普段は禁止しているテラス(廊下)を走ることを、職員が見ている時は許可したり、ホールの使い方を工夫したりしたので、園児どうしのトラブルが増えたということはなかったです。

シートで覆って保管してある除染した園庭の表土(汚染土)の山
■保護者の安心と子どもたちの笑顔のために
樋口/震災当日の在籍児は105名で現在は95名です(認可定員は80名)。今回の事故により数家族は県外に引っ越しましたが、4月に入園予定だった子どもたちはそのまま入園しました。したがって運営費は通常通り入りましたし、今回のことで資金面で困ったことはありませんでした。
樋口/先月、消防署の方に来ていただいて総合避難訓練を行いました。その際に署員の方からマニュアルの見直しや、地域の方との連携の話がありました。
実際、地域の方の助けがないとやっていけないということは今回の体験でよくわかったので、今後の訓練にいかしていきたいと思っています。
樋口/12月9日に外部講師の方を招き、「あそび歌コンサート」という手遊びや歌遊びをする行事を行いました。一時間程度のコンサートでしたが職員もとても楽しい時間をすごし、子どもたちは喰いつくように参加していました。そして何より一番嬉しかったのは、震災以降今まで見たことのないような、とっても素敵な笑顔を子どもたちはしていたのです。
講師の方に「大人が笑っていないと子どもは本気で笑わない」といわれ、大人が常に笑っていることの大切さを実感した出来事でした。
樋口/う~ん…、ここは大丈夫だよといいきれない、ここで生活していていいのか、という何ともいえない不安は正直にいうとあります。
ただ、実際にはこの地に暮らしている人がいて、子どもがいる限りは保育をしていかざるをえない。したがって、保護者の方にいかに安心して子どもを預けてもらえるかを考えながら日々の保育を行っています。
お話を伺った後、園内各所を見学させていただきましたが、放射能という目に見えないものによる高い数値がはじき出される以外はどこにでもあるような保育園の風景です。見学の時の雑談で聞いたところによると、園児たちは累積線量計を常時携帯しているとのことでした。取材時で最も多くの放射線を浴びた子どもは0・5ミリ(500μ)svだったそうです。
インタビュー中、コンサートの話をしている時に、樋口先生が思わず涙ぐみながら話をされた姿がとても印象的でした。
今回、2日間で計3園の保育園を訪問させていただきました。いずれの園も放射能という目に見えないものにより日常的に不安を抱えながら生活をしているという点では同じでした。しかし、政府による機械的な区分けにより、高線量の地域が何の指定もされないで、ただ原発から近いというだけで避難区域に指定されてしまったため、現在の生活も将来への展望も奪われてしまった地域があるという現実。これには非常にやるせない思いがしました。
そして、やはり現場に行かなければ知りえなかったこと、わからなかったことがあるということを痛感しました。訪問させていただいた3園の職員の皆様に共通していたのは「子どものために今できることをしよう」という、まさに保育の原理ともいえる考えに立って子どもたちと向き合っていることでした。このことは、保育という同じ仕事をしている、仲間である私たちにとって、とても誇りに思えました。
原発事故に始まったさまざまな困難や苦悩、苦労は今後も続くと思われます。この状況に少しでも手を差し伸べ、痛みを分かち合うことこそ、仲間である我々の使命だと思いました。
改めて、今回ご協力いただきました、南相馬市・原町聖愛保育園、北町保育所、そして伊達市・霊山三育保育園の皆様、本当にありがとうございました。
(城戸久夫・片岡敬樹/全私保連広報部)

園舎内の支柱と天井との間にできた隙間